
パーテクチュアル株式会社
代表取締役社長 中村稔
金型関連のものづくりに20年従事し、会社の社長としてリーダーシップを発揮。金型工業会と微細加工工業会にも所属し、業界内での技術革新とネットワーキングに積極的に取り組む。高い専門知識と経験を生かし、業界の発展に貢献しております。
詳細プロフィールは⇒こちら
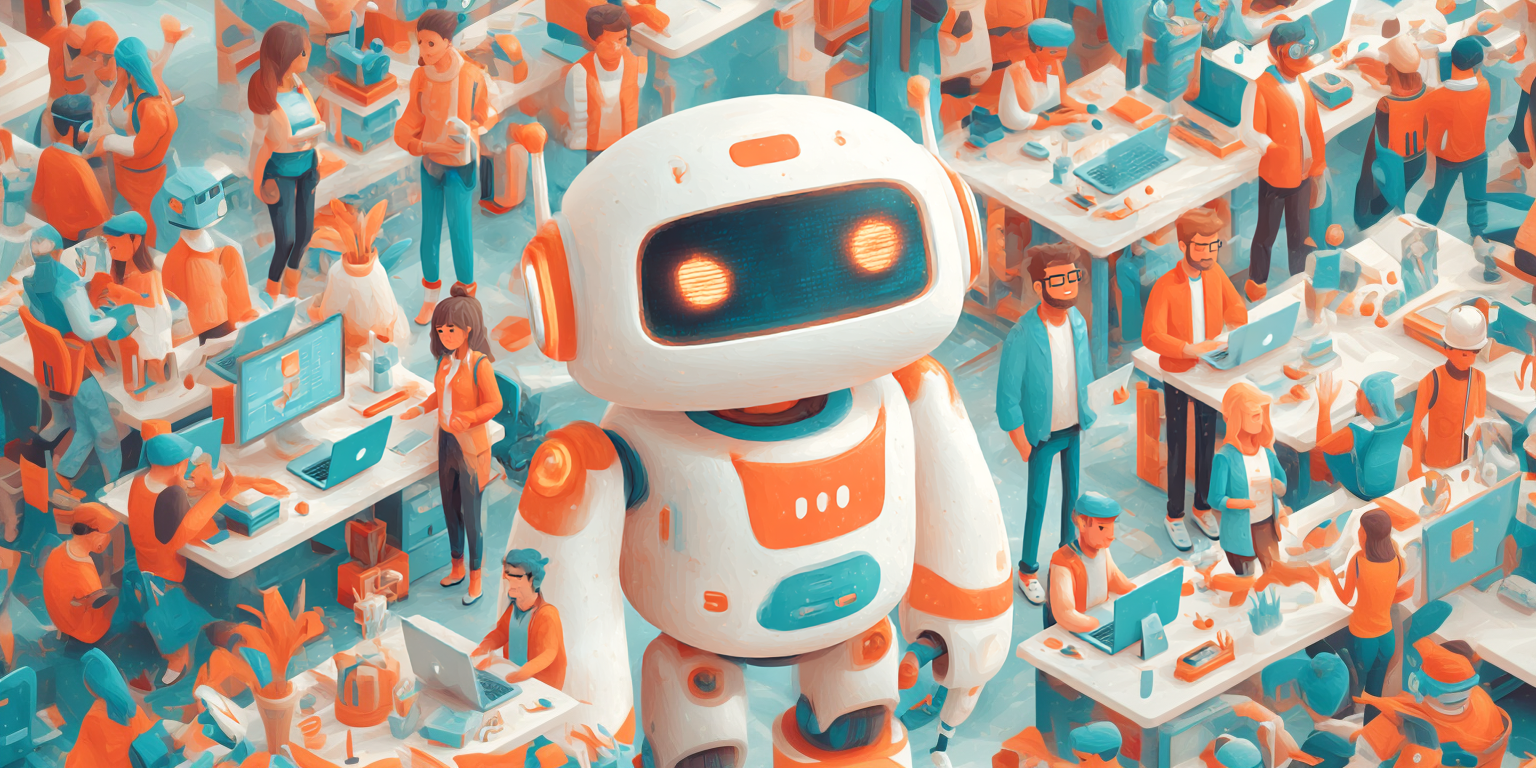

パーテクチュアル株式会社
代表取締役社長 中村稔
金型関連のものづくりに20年従事し、会社の社長としてリーダーシップを発揮。金型工業会と微細加工工業会にも所属し、業界内での技術革新とネットワーキングに積極的に取り組む。高い専門知識と経験を生かし、業界の発展に貢献しております。
詳細プロフィールは⇒こちら

皆さん、こんにちは!ニッシン・パーテクチュアルの中村です。
いやはや、毎日めまぐるしいスピードで技術が進んでいきますね。まるでSF映画の世界が、もう目の前に迫ってきているかのようです。私自身、製造業のど真ん中で3次元CADの導入やNC化の推進など、技術の進化と共に歩んできましたが、ここ最近のAIやロボティクス分野の発展には、本当に驚かされるばかりです。
かつて「ストリートファイター2」のコンボ技を必死で練習していた少年が、今ではリアルなロボットやAIの戦略を練っているなんて、なんだか不思議な気分ですよ(笑)。でも、あの頃に培った「どうすれば勝てるか?」「どうすればもっと先に進めるか?」という探求心は、今の仕事にも脈々と受け継がれている気がします。
さて、今日は2025年9月9日、まさに本日発表されたばかりの、ヒューマノイド、物理AI、そして自動運転に関する、とびっきり新鮮な情報をお届けしたいと思います。これらの技術が、私たち中小企業の現場、そして個人のキャリアに、これからどんな影響を与えていくのか。いつものように、ユーザー目線で、分かりやすく、そして楽しく解説していきますので、ぜひ最後までお付き合いください!
まずはこちらのニュースから。本日、兼松さんがフランスのEnchanted Tools社と提携し、ヒューマノイドAIロボット「ミロカイ」の国内販売を開始するという発表がありました。[1]
この「ミロカイ」、何がすごいって、まずその見た目が非常にユニークなんです。どこかアニメのキャラクターを彷彿とさせる、親しみやすいデザイン。身長123cm、体重26kgと、人間の子どもくらいのサイズ感ですね。従来の、いかにも「ロボットです」といった無機質なデザインとは一線を画していて、これなら医療や介護の現場、あるいは店舗の接客スタッフとしても、すんなり受け入れられそうです。
驚くべきは、その機能性。頭部のカメラで相手の表情や感情を認識し、それに応じて自身のディスプレイに豊かな表情を映し出す。さらに、最新のLLM(大規模言語モデル)を搭載し、自然な日本語での対話が可能だというのですから、もうこれは単なる作業ロボットではありません。まるで人間のようにコミュニケーションが取れる「パートナー」と言っても過言ではないでしょう。
私自身、これまで様々なロボットを見てきましたが、この「ミロカイ」には、何か新しい時代の到来を感じずにはいられません。かつて、手書きの図面を3次元CADに置き換えた時、あるいは職人の感覚をNCプログラムに落とし込んだ時のような、大きなパラダイムシフトが、今まさに起ころうとしている。そんな予感がするのです。
もちろん、課題もあります。約3kgの物を持ち上げたり、15kgまでの台車を牽引したりといった作業能力は、まだまだ限定的です。価格も気になるところですし、導入後のメンテナンス体制も重要になってくるでしょう。しかし、フランスの医療機関では、すでに患者へのケアで有効性が確認されているとのこと。これは、単なる技術的なデモンストレーションではなく、実社会での活用が始まっているという証拠です。
私たち中小製造業の現場でも、こうしたヒューマノイドロボットが活躍する日は、そう遠くないのかもしれません。例えば、部品のピッキングや簡単な組み立て作業、あるいは工場内の案内役など、応用範囲は無限に広がっています。完璧な性能を待つのではなく、「まずはここから試してみよう」という、ちょっとした遊び心とチャレンジ精神が、未来を切り拓く鍵になるのではないでしょうか。
さて、次に注目したいのが「物理AI(フィジカルAI)」というキーワードです。本日9月9日、計測自動制御学会(SICE)が主催するシンポジウムで、まさに「物理AIが拓くサイバーフィジカル・ヒューマンシステム」というテーマが掲げられています。[2]
「物理AI」と聞いても、あまりピンとこない方も多いかもしれませんね。平たく言えば、これまでのAIが主にデータや言語といった「バーチャルな世界」で学習してきたのに対し、物理AIは、カメラやセンサーを通じて「リアルな世界」の情報を直接学習し、行動するAIのことです。先ほど紹介した「ミロカイ」のようなロボットも、まさにこの物理AIの一種と言えるでしょう。
ここで一つ、面白い思考実験をご紹介したいと思います。哲学の世界で有名な「メアリーの部屋」という話です。
生まれながらに白黒の部屋で育ち、一度も「色」を見たことがない科学者メアリー。彼女は、色に関する物理的な知識(光の波長など)はすべて完璧に理解しています。さて、このメアリーが部屋から出て、初めて本物の「赤いバラ」を見たとき、彼女は何か新しいことを学ぶでしょうか?
この問いは、「知識として知っていること」と「実際に体験すること」の違いを浮き彫りにします。これまでのAIは、いわばこの「メアリーの部屋」の中にいたようなもの。膨大なテキストや画像データから「赤色」という概念は学習していても、それが実際にどんな「感じ」なのかは体験していませんでした。
しかし、物理AIは、まさにこのメアリーを部屋の外に連れ出すような試みです。ロボットが実際にモノに触れ、その硬さや重さ、温度を感じる。自動運転車が、雨の日のスリップしやすい路面を「体感」する。そうやって得られるリアルな物理情報と、それに対する自らの行動の結果を学習していくことで、AIはこれまでとは比較にならないほど、深く世界を理解していくのではないか。そんな期待が寄せられているのです。
私たちが製造業で培ってきた「現場感覚」や「職人技」。これらは、まさに長年の「物理的な体験」の積み重ねによって得られたものです。言葉や数式だけでは伝えきれない、あの絶妙なサジ加減。もしかしたら物理AIは、そんな暗黙知の世界にまで、足を踏み入れる可能性を秘めているのかもしれません。
もちろん、これも一筋縄ではいかないでしょう。現実世界は、予測不可能な出来事の連続です。突然の雨、路面の凹凸、人の飛び出し…。そうした無数の「ノイズ」の中で、いかに安全で的確な判断を下せるか。まだまだ乗り越えるべき壁は高いですが、この挑戦の先に、私たちの社会を根底から変えるような、とてつもないイノベーションが待っている。私はそう信じています。
そして最後は、自動運転技術の最新動向です。こちらも本日、ドイツのミュンヘンで開催されているIAAモビリティ2025で、非常に興味深い発表がありました。自動運転技術のパイオニアであるDeepRoute.aiが、VLA(視覚・言語・アクション)モデルを搭載した新しいプラットフォーム「DeepRoute IO 2.0」を発表したのです。[3]
「VLAモデル」という言葉、初めて聞く方も多いかもしれませんね。これは、従来の自動運転AIが、主にカメラの映像(視覚情報)を解析して運転操作を判断していたのに対し、そこに「言語」の能力を組み合わせた、新しいアプローチです。
一体どういうことか? 例えば、前方に「この先、道路工事中」という看板があったとします。これまでのAIは、その看板の「文字」を正確に読み取ることはできても、その「意味」を深く理解し、人間のように柔軟な対応をすることは苦手でした。しかし、VLAモデルは、大規模言語モデル(LLM)の能力を活用することで、「道路工事中だから、少し速度を落として、作業員に注意しながら走行しよう」といった、より人間らしい、文脈を理解した判断が可能になるというのです。
さらに驚くべきは、このVLAモデルが「Chain-of-Thought(思考の連鎖)」という推論能力を持っている点です。これは、AIが「なぜ」その判断を下したのか、その思考プロセスを人間が理解できる形で説明できる、ということ。例えば、「前方の車両が急ブレーキをかけたので、安全距離を確保するために減速しました」といった具合です。これは、自動運転の安全性を担保し、社会的な信頼を醸成する上で、非常に重要な技術だと私は考えています。
DeepRoute.aiは、すでにこのシステムを搭載した車両を10万台以上も納入しているというのですから、その実用性の高さが伺えます。LiDAR(レーザーセンサー)を使う構成と、カメラだけで実現する構成の両方に対応できる柔軟性も、多くの自動車メーカーにとって魅力的でしょう。
私自身、長年ものづくりの現場で、機械の「自動化」に取り組んできました。NC工作機械も、言ってみれば一種の自動運転です。しかし、そこには常に「想定外」の事態がつきものでした。材料のわずかな歪み、刃物の摩耗、プログラムの小さなミス…。そうした予期せぬトラブルを乗り越えるには、やはり人間の「経験」と「判断力」が不可欠でした。
このVLAモデルの話を聞いて、私は、自動運転技術がようやく、その「人間の領域」に足を踏み入れ始めたのではないかと感じています。単に決められたルールに従って走るだけでなく、状況を理解し、予測し、そして時には「かもしれない運転」のような、人間的な配慮さえもできる。そんな未来が、もうすぐそこまで来ているのかもしれません。
もちろん、これもまた完璧ではありません。特に、ヨーロッパの複雑な道路環境や、国ごとに異なる交通文化にどう適応していくのか。まだまだ課題は山積みです。しかし、この挑戦は、単に移動を便利にするだけでなく、交通事故の削減、高齢者の移動支援、そして物流の効率化など、私たちの社会が抱える多くの課題を解決する、大きな可能性を秘めているのです。
さて、本日はヒューマノイド、物理AI、自動運転という3つのテーマで、最新の技術動向をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。
感情を表現するロボット、現実世界で学ぶAI、そして人間のように考える自動運転…。まるでSFのような話ばかりでしたが、これらはすべて、今日この日に、現実の世界で起きていることです。そして、これらの技術は、もはや一部の巨大企業だけのものではありません。
私たち中小企業も、そして私たち一人ひとりも、これらの技術と無関係ではいられない時代が、もう始まっています。大切なのは、完璧なものが登場するのを待つのではなく、今ある技術を「まずは使ってみる」「試してみる」という姿勢ではないでしょうか。
私自身、生成AIの活用を推進する中で、たくさんの失敗を繰り返してきました。でも、その一つ一つの失敗が、次の一歩に繋がる貴重な学びとなっています。セミナーで皆さんの前でお話しできるのも、そうした試行錯誤の経験があるからです。
今回ご紹介した技術も、すぐに私たちの仕事をすべて奪うようなものではありません。むしろ、私たちの能力を拡張し、これまでできなかったことを可能にしてくれる、強力な「ツール」です。この新しいツールをどう使いこなし、自分たちの仕事や生活を、より豊かに、より創造的にしていくか。今、私たち一人ひとりに、その「問い」が投げかけられているのだと思います。
激流のような技術の進化に、時には目が回りそうになることもありますが、これからも必死にしがみついて学び続け、皆さんに有益な情報をお届けしていきたいと思っています。一緒に、このワクワクする未来を創っていきましょう!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それでは、また!
ニッシン・パーテクチュアル株式会社
代表取締役社長 中村 稔
[1] 兼松株式会社プレスリリース「兼松、仏 Enchanted Tools 社とヒューマノイド AI ロボット「ミロカイ」の国内販売契約を締結」2025年9月8日
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000092359.html
[2] 公益社団法人 計測自動制御学会「SICシンポジウム2025「物理AIが拓くサイバーフィジカル・ヒューマンシステム」」2025年9月9日
https://www.sice.jp/info/info_event/event_20250909.html
[3] DeepRoute.ai プレスリリース「DeepRoute.ai、量産対応のDeepRoute IO 2.0プラットフォームをIAA 2025に出展」2025年9月9日
https://jp.prnasia.com/story/125308606-3.shtml
タグ: #ヒューマノイドロボット #物理AI #自動運転 #VLAモデル #ミロカイ #DeepRoute #中小企業 #製造業 #AI活用 #技術革新 #未来技術
コメント