
パーテクチュアル株式会社
代表取締役社長 中村稔
金型関連のものづくりに20年従事し、会社の社長としてリーダーシップを発揮。金型工業会と微細加工工業会にも所属し、業界内での技術革新とネットワーキングに積極的に取り組む。高い専門知識と経験を生かし、業界の発展に貢献しております。
詳細プロフィールは⇒こちら


パーテクチュアル株式会社
代表取締役社長 中村稔
金型関連のものづくりに20年従事し、会社の社長としてリーダーシップを発揮。金型工業会と微細加工工業会にも所属し、業界内での技術革新とネットワーキングに積極的に取り組む。高い専門知識と経験を生かし、業界の発展に貢献しております。
詳細プロフィールは⇒こちら
工場の自動化と人手不足解消の切り札として注目される搬送ロボット。しかし、その導入には「従業員の安全をどう確保すればいいのか?」という不安が付きまといます。この記事では、これから搬送ロボットの導入を検討しているあなたのために、守るべき安全基準の国際規格から、現場ですぐに実践できる具体的な安全対策までを網羅的に解説。安全で生産性の高い、次世代の工場を実現するための知識がすべて手に入ります。
搬送ロボット導入において、安全基準の遵守は絶対条件といえます。なぜなら、安全対策は単に事故を防ぐだけでなく、工場の生産性維持と企業の社会的信頼に直結する重要な要素だからです。人とロボットが協働する環境では新たなリスクが生まれ、万が一の事故は事業継続を揺るがしかねません。未来への投資として安全基準を正しく理解し、万全の対策を講じることが求められます。
搬送ロボットは人手不足解消の強力な解決策ですが、同時に新たなリスク管理が求められることを認識しなければなりません。これまで人が担っていた作業の自動化は生産性を飛躍的に向上させる一方、機械ならではの予期せぬ動きや、作業員との接触といった新たな危険性が生まれるからです。例えば、倉庫内での24時間稼働は大きなメリットですが、人とロボットの作業動線が交錯するエリアでのルールが曖昧だと、常に事故のリスクが付きまといます。メリットを最大化するためには、これらのリスクを正確に把握し、対策を講じることが不可欠です。
人とロボットが協働する環境では、これまで想定されなかった事故が発生する可能性があります。これは、人は「ロボットは安全に止まるはず」と思い込み、ロボットは人の複雑な動きを完全には予測できないという、認識のズレから生じることが多いのです。実際に、搬送ロボットの死角に作業員が入り込み衝突する事故や、積荷の落下による物損事故などが報告されています。これらの多くは、少しの油断やルールの形骸化が引き金となっています。他社の事例から学ぶことで、自社に潜むリスクを予見し、未然に防ぐことが重要でしょう。
安全対策を単なるコストとして捉えるべきではありません。これは、企業の未来を守り、成長を加速させるための「戦略的投資」なのです。なぜなら、徹底した安全管理は、従業員が安心して働ける環境を構築し、結果として定着率や生産性の向上に繋がるからです。例えば、安全対策が万全な工場は、従業員のエンゲージメントを高めるだけでなく、取引先や顧客からの信頼獲得にも貢献します。事故による稼働停止やブランドイメージの毀損といった損失を防ぐためにも、安全対策は最優先で取り組むべき投資といえます。
安全基準を正しく適用するためには、まず搬送ロボットの種類と特性を理解することが第一歩となります。代表的なものに「AGV」と「AMR」がありますが、両者は走行方式が異なり、それに伴い安全対策のポイントも変わってくるからです。それぞれの違いを知ることで、自社の環境に最適なロボットを選定し、適切な安全基準を適用するための土台となる知識を身につけましょう。
AGV(Automated Guided Vehicle)は、床に貼られた磁気テープや QRコードといったガイドに沿って走行する搬送ロボットです。決められたルートを正確に移動するため、動線の予測がしやすく、導入コストを比較的抑えられる点がメリットでしょう。一方で、ルート上に人や障害物があると停止してしまい、生産ライン全体の停止に繋がる可能性があります。そのため、AGVを安全に運用するには、走行経路と人の作業エリアを明確に分離したり、ルート上の安全を確保したりする物理的な対策が特に重要になります。
AMR(Autonomous Mobile Robot)は、搭載されたセンサーやAIで周囲の環境を認識し、自ら最適なルートを判断して走行するロボットです。AGVと違い、障害物を自律的に回避できるため、人や設備が頻繁に移動する複雑な環境でも柔軟に稼働できるのが最大の強みです。しかし、その自律性ゆえに動きの予測が難しい側面もあり、高度な安全機能が求められます。人や障害物を確実に検知するセンサーの性能や、衝突を回避する制御システムの信頼性が、AMRの安全性を担保する上で極めて重要です。
自社に最適なロボットを選ぶ際は、生産性だけでなく安全性の観点から検討することが失敗しないための鍵です。まず、工場のレイアウト変更が少ない固定的な環境であれば、動線管理がしやすいAGVが適しているかもしれません。一方、人とロボットが同じ空間で作業する、あるいは頻繁にレイアウトが変わるような動的な環境では、障害物回避能力に優れたAMRが適しています。どちらを選ぶにせよ、導入前にリスクアセスメントを行い、それぞれのロボットの特性に合った安全対策を計画することが最も重要です。
【早わかり比較表】AGV vs AMR
| 項目 | AGV(無人搬송車) | AMR(自律走行搬送ロボット) |
|---|---|---|
| 走行方式 | 磁気テープなどのガイドに沿って走行 | 地図情報を基に自律的に走行 |
| 障害物回避 | 停止する | 迂回して走行を続ける |
| 柔軟性 | △(ルート変更に手間がかかる) | ◎(ソフトウェアで簡単にルート変更可能) |
| 導入コスト | 比較的安価 | 比較的高価 |
| 適した環境 | 固定的なレイアウトの工場 | 人やモノが動く複雑な環境 |
搬送ロボットを安全に運用するためには、世界的に認められた安全規格を理解し、遵守することが不可欠です。これらの規格は、過去の事故事例や専門家の知見に基づき、ロボットが満たすべき安全要件を定めたものです。特に国際標準である「ISO 3691-4」と、それを基にした日本の「JIS D 6802」は必ず押さえておくべき規格。これらを守ることは、法的責任を果たすだけでなく、従業員の命を守ることに直結します。
「ISO 3691-4」は、無人搬送車(AGV)や自律走行搬送ロボット(AMR)を含む産業用トラックの安全に関する国際規格です。この規格の目的は、設計段階から運用、メンテナンスに至るまで、ロボットのライフサイクル全体で危険性を体系的に取り除くことにあります。グローバルに事業展開する上でも、この国際標準への準拠は必須といえるでしょう。この規格が求める主な要求事項は以下の通りです。
「JIS D 6802」は、国際規格であるISO 3691-4を基に作成された、日本の産業規格(JIS)です。基本的な安全要求事項はISO規格に整合していますが、日本の労働環境や法規制の実情に合わせて最適化されている点が特徴です。例えば、日本の工場で一般的に使用される機器との連携や、国内の安全基準に関する細かな要求が盛り込まれています。国内で搬送ロボットを導入し、安全認証などを取得する際には、このJIS規格への準拠が事実上の標準となります。
特定の安全規格だけでなく、日本のすべての事業者は「労働安全衛生法」を遵守する義務があります。この法律は、事業者が労働者の危険や健康障害を防止するための措置を講じることを定めており、搬送ロボットの導入も例外ではありません。具体的には、ロボットの導入にあたり、事業者には適切なリスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて安全対策を講じる責任があります。万が一、安全対策を怠って労働災害が発生した場合、事業者は法的な責任を問われることになりますので、細心の注意が必要です。
事故ゼロの現場を実現するためには、「リスクアセスメント」の実施が不可欠です。これは、現場に潜む危険性を科学的に特定・評価し、対策の優先順位を決める手法のことです。難しく聞こえるかもしれませんが、以下の3つのステップで進めることで、網羅的かつ効果的に実施できます。
リスクアセスメントの第一歩は、ロボットの稼働エリアにどのような危険が潜んでいるかを具体的に洗い出す「危険源の特定」です。作業員や関係者と協力し、「ロボットと人が衝突する可能性はないか」「搬送物が落下する危険はないか」「狭い通路で挟まれるリスクはないか」といった視点で、考えられる限りの危険をリストアップします。例えば、見通しの悪い曲がり角や、人とロボットの動線が交差する場所などが、特に注意すべき危険源となります。思い込みを捨て、あらゆる可能性を想定することが重要です。
危険源を洗い出したら、次はそのリスクの大きさを評価する「リスクの見積もり」を行います。これは、特定した各危険に対して、「事故が発生する可能性(頻度)」と「発生した場合のけがの重篤度」をマトリクスなどを用いて点数化し、リスクの優先順位を決定する作業です。例えば、「頻繁に発生し、重傷に至る可能性がある」リスクは最優先で対策すべき、と判断できます。この評価により、限られたリソースをどこに集中すべきかが明確になり、効果的かつ効率的な安全対策を計画することが可能になります。
リスクの優先順位が決まったら、いよいよ具体的な対策を検討する「リスク低減措置」のステップに進みます。優先度の高いリスクから順に、「そのリスクを完全に取り除くことはできないか」「取り除けない場合、どうすればリスクを許容できるレベルまで下げられるか」を考えます。例えば、衝突リスクが高い場所には物理的な安全柵を設置する、システムの改修を行う、作業手順を見直す、といった対策が考えられます。ここで検討された対策が、現場の具体的な安全ルールや設備投資の計画となっていくのです。
リスクアセスメントで計画した対策を、現場で確実に実行することが事故防止の鍵を握ります。安全対策には、設備で物理的に危険を防ぐアプローチ、システムで制御するアプローチ、そして人の教育やルールで管理するアプローチの3つがあります。これらを単独ではなく、複合的に組み合わせる「多重防護」の考え方を取り入れることで、現場の安全レベルを飛躍的に高めることが可能になります。
最も基本的かつ効果的なのが、安全柵やセーフティライトカーテン(光電センサー)といった物理的な安全対策です。これらは、ロボットの稼働エリアと人の作業エリアを明確に区切り、危険な領域への侵入を物理的に防ぐ役割を果たします。具体的には、以下のような物理的な対策が有効です。
ロボット自体のシステムによる安全対策も進化しています。高性能なセンサーで人や障害物を検知し、自動で減速・停止する衝突防止機能は、特にAMRにおいて中心的な役割を担います。さらに、見落とされがちですが、ネットワークに接続されたロボットへのサイバー攻撃対策も重要性を増しています。以下のような対策が挙げられます。
最新の設備やシステムを導入しても、それを使う人の安全意識が低ければ事故は防げません。そのため、ロボットの操作方法だけでなく、危険性や緊急時の対応手順について、全作業員に定期的な教育を実施することが不可欠です。ルールを形骸化させず、常に改善していく組織的な取り組みこそが、持続的な安全を実現する鍵です。
この記事では、搬送ロボットを導入する上で不可欠な安全基準について、その重要性から規格の解説、そして現場での具体的な実践方法までを解説しました。安全対策は、単なる規制対応やコストではなく、従業員の命を守り、企業の生産性と信頼性を向上させるための重要な経営課題です。国際規格や法律を正しく理解し、自社の状況に合わせたリスクアセスメントと具体的な対策を講じることで、人とロボットが安全に共存する、競争力のある次世代のスマート工場を実現しましょう。
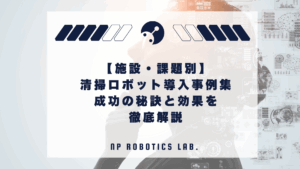


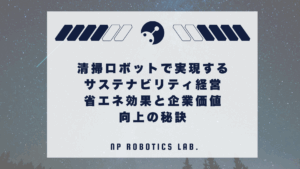

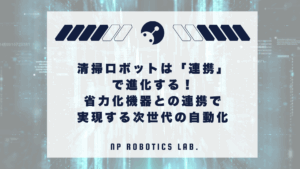

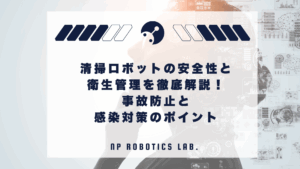
コメント